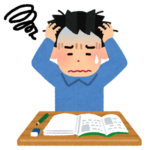前向きな姿勢を大切に
こんにちは!担任助手の荒木です。
夏休みは有意義に過ごせましたか?
東進の夏イベントも終わってしまいました。
みなさんとても頑張ってポイントを稼いでいましたね!
夏に頑張ったことは、これから結果として少しずつ現れてきます。
逆にここでやめてしまえば、成長はなくなります。
自分を信じて、引き続き勉強頑張っていきましょう。
私は、まだ夏休みの途中ですが、先日、熊大付属小学校に一日お邪魔し、実際の授業の様子を見学する観察実習に行ってきました。
私は、1年生のクラスで、授業や休み時間、給食や委員会活動などの子どもたちの様子を一日、間近で観察することができました。
普段は大学で教育学の理論などを学んでいるのですが、やはり実際の現場を自分の目で見ると、教科書ではわからない学びがたくさんあると感じました。
実習を通して
観察実習の中で、授業中の児童の発言の多さがとても印象に残りました。
例えば、発表する時間では、多くの児童が手を挙げたり、発表した一人に対してほかの座っている児童が賛成・反対を言ったりして活発な意見の交流が行われていました。先生の一つ一つの発言にもすぐ返していました。
少し騒がしい状況になってしまうこともありましたが、これは、児童一人一人の勉強に対する前向きな姿勢の現れであり、大切なことだと思いました。
勉強を「やらされている」というよりは「知りたい!」「できるようになりたい!」という気持ちが前面に出ていて、その姿勢がとても印象的でした。
皆さんの中にも小学生の時はよく手を挙げて発表していたという人が多くいると思います。
この実習を通して気づいたことは、学びにおいて
「主体性」
がどれほど大切かということです。
小学生のように「なんで?」「もっと知りたい!」という好奇心を持つことが、学びを深める第一歩なのだと感じました。
主体的な学び
皆さんにも主体的な学びを意識してほしいと思います。
例えば英語の長文を読むときに、「ただ設問を解くだけ」ではなく「なぜこの単語が使われているのか」「この表現はどういうニュアンスなのか」と自分で疑問を持って調べることができれば、理解は格段に深まります。
数学の問題も同じで、答えが合っているかどうかだけでなく「どうしてこの公式が成り立つのか」「他の方法では解けないか」と考えることで、知識が「使える力」に変わっていくのです。
受験勉強においても、つい「やらないといけないから」「宿題だから」という気持ちで机に向かいがちです。
でもそれでは学びが受け身になってしまい、なかなか身につきません。
「親や先生に言われるから」というような自分以外のものを軸として勉強しても、短期的な効果はあっても、持続性はないし、集中力はすぐ切れてしまい諦めがちになります。
動機づけ
人間の行動には、内発的動機づけと外発的動機づけというものがあります。
内発的動機付けとは、自身の知的好奇心や理解欲求、向上心などの内的要因が動機となって行動を起こすことであり、
外発的動機付けは報酬や罰、他者からの評価などの外的要因が動機となって行動を起こすことです。
勉強するときにも、「絶対ここに合格したい」というような内発的な動機付けが自分の中にあれば、長期的な学習継続と深い理解をもたらしてくれます。
勉強に対して主体的になることは、最初は少し大変に思えるかもしれません。
でも、「ただやる」から「自分から学ぶ」に切り替えた瞬間に、勉強の見え方はガラッと変わります。
今回の実習で学んだことは、教育者としての目線だけでなく、自分自身が学ぶ立場としても大きなヒントになりました。
おわりに
これから受験を控えるみなさんにもぜひ、「学ぶことを楽しむ・勉強に対して前向きな姿勢」を大事にしてほしいと思います。
点数や結果を追い求めることも大切ですが、「理解できた!」「自分で考えられた!」という小さな達成感を積み重ねていくことが、最終的には大きな成長につながります。
受験勉強は大変なことも多いですが、学ぶ姿勢を工夫すれば必ず前向きになれます。私も今回の経験を活かし、これからも一緒に頑張っていきます!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。