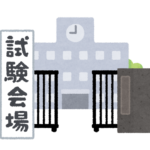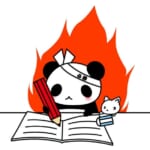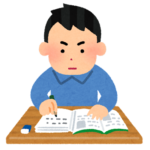ナノカーボン材料学研究室〜酸化グラフェンの基礎研究〜
こんにちは!担任助手の井上です!
あと1週間もすれば11月ですね。とても早いものです。
急激に寒くなってきたので、体調に気をつけて過ごしましょう!
ナノカーボン材料学研究室
今回は、私が大学で所属している工学部・材料応用化学科・物質材料工学プログラム・ナノカーボン材料学研究室で行っている研究について紹介します。
ちょっと難しそうなタイトルですが、できるだけわかりやすく説明します!
酸化グラフェンってなに?
「グラフェン」は、炭素原子が蜂の巣のように並んだ、とても薄いシート状の物質です。
たった1枚の原子層なのに、強度は鉄よりも強く、電気もよく流すという、夢のような素材です。
でも、そのままだと扱いが難しいので、酸素官能器をくっつけて「酸化グラフェン(GO)」という形にして使うことがあります。
この酸素官能器があることで、水に溶けやすくなったり、他の物質と混ぜやすくなったりするんです。
私の研究テーマ
私が取り組んでいるのは、
「超音波の周波数を変えて、酸化グラフェンの“サイズ”をコントロールできないか?」
という研究です。
酸化グラフェンは、作製時に超音波処理を行います。
通常、28〜45kHzくらいの低い周波数で行います。
しかし、私は、「100kHzの高周波でやってみたらどうなるのか?」を実験で確かめています。
狙いは、
「酸素官能器の性質を保ったまま、より大きなグラフェンを作れないか」というところです。
もし成功すれば、電子材料やセンサーなどへの応用の幅が広がる可能性があるんです!
どうやって確かめるの?
研究では、作製した酸化グラフェンの性質をいくつかの方法で調べます。
粒度分布測定:粒の大きさがどれくらいかを測る
原子間力顕微鏡(AFM):グラフェンの「厚み」や「形」を原子レベルで観察する
UV測定:光の吸収の違いから、構造変化をチェックする
赤外分光法(FTIR):どんな酸素の種類がくっついているかを調べる
他にもまだありますが、このような測定法を総合して判断することで、実験結果の信頼性を高めています。
また、試料は0.001 wt%というすごく薄い濃度に調整して測定します。
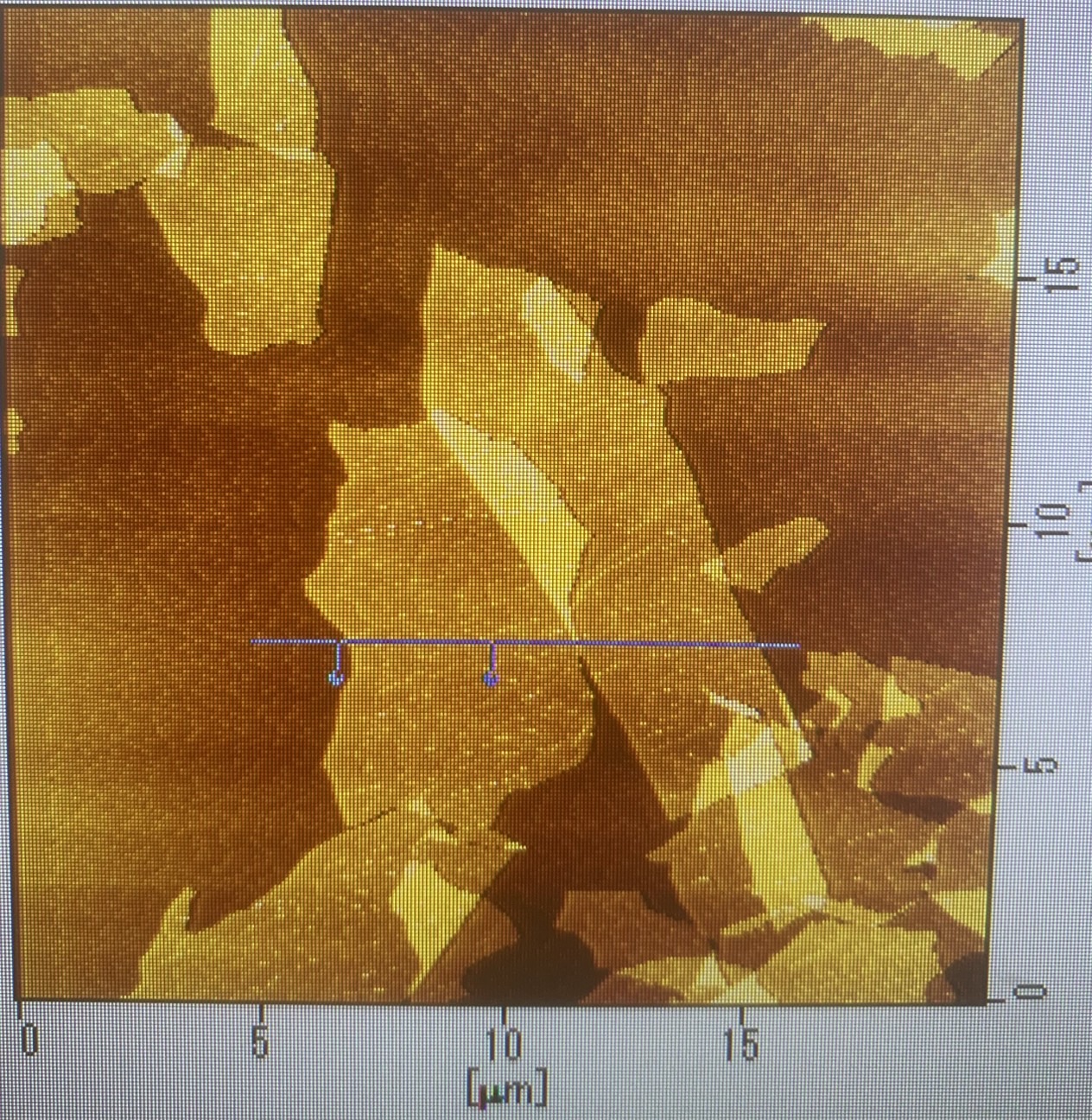 これは実際に私がAFMで観測した酸化グラフェンになります。縮尺の単位がμmと非常に小さいですが、28〜45kHzで超音波処理したものより、ものすごく大きいです!
これは実際に私がAFMで観測した酸化グラフェンになります。縮尺の単位がμmと非常に小さいですが、28〜45kHzで超音波処理したものより、ものすごく大きいです!
基礎研究と応用研究のちがい
こういった研究は、すぐに製品化されるようなものではありません。
いわゆる「基礎研究」と呼ばれる分野で、新しい発見や原理を理解することを目的にしています。
それに対して、「応用研究」は、その知識を使って実際にものを作る研究です。
例えば、「この酸化グラフェンを使って高性能な電池を作ろう!」といったものですね。
どちらも科学を前に進めるうえで大切なステップです。
最後に
今回紹介したのは、熊本大学の材料応用化学科にある研究室の1つのテーマです。
同じ学科の中にも、金属・有機材料・バイオ・高分子など、さまざまな分野があります。
自分が「これ面白そう!」と思えるテーマに出会えると、研究は本当に楽しくなります。
みなさんもぜひ、自分に合った、頑張れる学部・学科を探してみてください!

熊本大学 工学部
玉名高校 出身