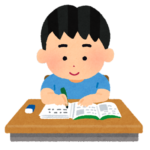メタ認知で効率アップ!!
みなさんこんにちは!担任助手の木下碧人です。
10月に入り、本格的に単元ジャンル別演習などに積極的に取り組む姿をたくさん見かけるようになりました。
でも、ちょっとだけ自分のやり方を見直してみてください。
「解く → 丸付け → 点数を見て一喜一憂 → 軽く解説を読んで納得 → おしまい!」 …なんていう流れ作業になっていませんか?
もし少しでもドキッとしたなら、今回のブログをしっかり見てほしいです。
今日は、私が大学の授業で学んでいる『メタ認知』という考え方を使って、単元ジャンル演習などの効果を大きく高める方法を紹介します!
そもそも『メタ認知』って何?
「メタニンチ…?何かの必殺技?」と思った人もいるかもしれません。
すごく簡単に言うと、メタ認知とは「もう一人の自分が、客観的に自分を観察している」ような状態のことです。
勉強で言えば、問題を解いている自分を、頭の中のもう一人の自分が見ていて、
「お、今、集中できているな」
「なぜ、この選択肢を選んだんだ?」
「この問題で時間をかけすぎているぞ」
と、自分の思考や行動を冷静に分析・コントロールする力のことです。
このメタ認知、実は成績を伸ばす上でめちゃくちゃ重要な力だと、教育心理学の世界では言われています。そして、この力は単元ジャンル別演習などの問題演習でこそ、最大限に鍛えることができるんです。メタ認知を使った効率のいい勉強の方法を教えます。
【ステップ1】原因分析:なぜ間違えたのか?
まずは、ミスの原因を徹底的に突き止めます。選択肢はこんな感じです。
① 知識不足:(単語、公式、年代などを単純に知らなかった)
② 読解ミス:(問題文や本文の意味を正しく読み取れなかった)
③ 思考プロセスミス:(知識はあったが、考え方・解き方の筋道を間違えた)
④ 時間不足:(解き方は分かったはずが、時間がなくて解けなかった)
⑤ ケアレスミス:(計算ミス、マークミスなど、完全に不注意)
ここで大事なのは、安易に「ケアレスミス」という結論に逃げないこと。「なぜその不注意が起きたのか?(見直す時間がなかった?焦っていた?)」まで考えると、本質的な原因が見えてきます。
【ステップ2】思考プロセスの再現
「勉強しているのに成績が上がらない」場合以外にも「成績が上がっている!」という人こそメタ認知をしてみましょう!
成績が上がっているときにメタ認知を行うことで、「今後も成績が上がり続ける人」になれます。
このような場合は、以下のように考えてみてください。
・何をしたら成績が上がったのか分析する
・どのテキストの、どの単元を、どれくらい(ページ数、回数)したら、何の(どの単元)成績・点数がどれくらい上がったか。
・どれくらい勉強時間を取ったかを分析する
・前回(成績が上がる前)と変えたこと(変わったこと)はないか
成績が上がったときは「成功要因の分析」を、まだ上がっていないときは「原因分析」をしてみましょう。
成功要因を客観的に認知できれば、次回も同じように考えることで成績を上げることができます。
「なんでかわからないけど成績が上がった」状態が一番危険なので、しっかりと分析を行えるように普段から意識することを心がけてください。
私のおすすめ:東進の一日の終わりの荷物を片付けたりしているときや下校しているときにこのように今日は何を勉強して何を学んだのかをしっかり考えると、「今日意外と全然何もしてないな」などと危機感を感じることができるのでおすすめです。
【ステップ3】対策:じゃあ、次どうする?
最後に、具体的なアクションプランを考えます。「次から気をつけよう」という精神論ではダメです。
(原因が①なら)→ 「高速基礎マスターを今週末もう一度100%にする」
(原因が②なら)→ 「長文問題では、根拠となる一文に必ず線を引く練習をする」
(原因が④なら)→ 「大問1個あたりの目標時間を設定し、普段の演習から意識する」
このように、具体的で、すぐに行動に移せるレベルまで落とし込みましょう。
この3ステップを繰り返していくと、過去問はただの「力試しのテスト」から、「自分の弱点がすべて詰まった、最高の自分専用参考書」に変わります。
最後に
最初は少し面倒に感じるかもしれません。でも、このひと手間をかけるかどうかで、これからの伸びが全く違っていきます。
メタ認知をこの時期に使いこなせていると将来コミュニケーション能力の向上にも大きくつながるので損は絶対に無いです!!
最後まで読んでくださりありがとうございました。