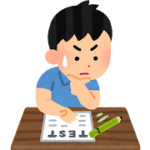私がしていたノートの取り方
こんにちは!担任助手の土山です。
夏休みも終わり、2学期が始まりましたね。
突然ですが、学校で授業を受けているとき、東進で講座を受講しているとき、皆さんは何を意識してノートをとっていますか?
ノートを取らないという人もいるかもしれませんが、私はノートをとることで効率よく勉強することができると考えています。
3年生は学校の課外、1,2年生は新年度の講座が本格的に始まります。
これからノートをとる機会が増えるのではないかと思いブログを書きました。
最後まで読んでいたただけると嬉しいです。
復習前提でノートをとる
どんな目的でノートをとっていますか?
私は復習をするためにノートはあると思っています。(今回のブログで一番伝えたいことです!)
復習を効率よくできるノートを作るために私は2つのことを意識しています。
1つ目は自分の言葉で書くことです。
授業中、板書に加えて、「○○は△という意味」「言い換えると□□」というメモをよく書きます。
これは、自分が本当に理解できているかを確認する作業にもなります。自分の言葉で説明できないということは、まだ理解が浅い証拠なので、授業後に復習が必要だとわかります。
もう1点は余白を残すことです。
ノートいっぱいに書きこむのではなく、左右どちらかにスペースを作っておきましょう。
そのスペースに、授業後に問題集を解いていて「あ、この公式ってこういう使い方もあるんだ」と気づいたら、その余白に書き足します。
また、わからなかった部分には「?」マークをつけて、後で先生に質問した内容を余白に書き加えています。
こうすることで、ノートがどんどん自分専用の参考書に育っていく感覚があります。
私もこのブログを書く過程で知ったことですが、左側を3分の1くらいあけて、そこに後から気づいたことや、関連する内容を書き込むノートの取り方を「コーネル式ノート」と呼ぶそうです。
板書をただ写していませんか?
ノートをとるとき先生が書いた内容をただ丸写ししていませんか?
板書を写すことに必死で内容が理解できていないことはありませんか?
高校の授業は50分あり、授業一回分の板書量はかなり多いです。
それらをすべて写していると当然時間が足りなくなってしまいます。
授業中は完璧なノートを作ろうとせず要点を押えることに集中しましょう。
数学を例にすると、私は定義、定理はしっかりと板書を写し、証明は該当する教科書のページを書き、気づき(証明の中で難しいと感じたことなど)を添えてまとめていました。
丁寧に書いたノートが効率的なノートとは限りません。
日付と科目を必ず書く
些細なことのようですが、これが意外と重要です。
後で見返したときに、いつの授業なのかわからないと、教科書やプリントと照らし合わせるのが大変になります。
私は最初のページに日付、曜日、単元名まで書くようにしています。
例えば「10月17日(金)化学・酸化還元反応」という感じです。
こうすることで、テスト範囲が発表されたときにどのページを見ればいいか一目でわかりますし、復習計画も立てやすくなります。
色を使いすぎない
カラフルなノートは見栄えがいいですが、作ることが目的になってしまいがちです。
私は基本的に黒と赤、せいぜい青の3色までに抑えています。
具体的には、黒は通常の内容、赤は絶対に覚えるべき重要事項や公式、青は補足情報や注意点という感じで使い分けています。
蛍光ペンも要注意です。
高校時代の私は、ノートを見返すときに重要な部分に蛍光ペンを引いていたのですが、気づいたらページ全体が青くなっていました。本当に大事な部分だけに絞って使うことが大切です。
目安としては、1ページに3箇所程度までにしておくと、後で見返したときに重要ポイントがすぐわかります。
最後に
今回はノートの取り方をテーマにブログを書いてみました!
ノートの取り方に正解はありませんが、ノートをとることだけが目的にならないように注意してください!
大切なことは自分にとって復習しやすいノートをつくることです。
最初は試行錯誤が必要かもしれませんが、いろいろ試してみて、自分なりのスタイルを見つけてください。このブログが参考になったらうれしいです。
効率的な勉強方法を身につけていきましょう!