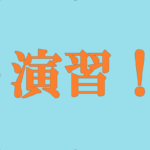問題集だけで大丈夫...?
こんにちは!担任助手の姉川です。
最近は朝と夜の冷え込みが厳しくなり、体調を崩しやすい時期です。入試本番に向けて、風邪をひかないよう、手洗いうがいや体調管理には十分気を付けましょう!
最近感じること...
東進で皆さんの学習状況を見ていると、「問題集や参考書を使って学習を進めている人」が増えているなと感じています。
自分のペースで学習を進めるのは、受験を乗り切る上で欠かせない力です。
しかし!!
その一方で、この時期に「問題集を何度も解いたのに、模試や実戦的な問題で手が止まってしまう...」という悩みに直面している人も多いと思います。
なぜ「完璧にしたはずの問題集」が入試で通用しないのか?
皆さんが問題集を使って身につけた知識は、決して無駄ではありません。それは、問題を解くための"ツール"をしっかりと身に着けた証拠になります。
しかし、入試問題は単なるツールの確認するだけのテストではありません。
「どの道具を、どのような順番で使うか」を判断し、正しく解き進められるかを確認するテストです。
つまり、入試問題を解けるようにするには、問題集や参考書を解くだけでは不十分ということになります。
実際に、入試の数学では、問題を解き始める前に、脳内で必ず以下の三段階の思考プロセスを辿る必要があります。
Step1: 問題の分野特定→ 目の前の問題がどの分野の知識を使うべきかを判断する。
Step2: 知識選択→ 特定した分野の中から、最も有効な定理や公式を選び出す。
Step3: 実行・計算→ 選んだ知識を組み合わせ、正確に計算を最後まで実行する。
これをもとに考えてみましょう!
問題集は、単元別・分野別に構成されています。
つまり、最初に「これはこの分野の問題だよ」とヒントが書いてある状態で問題を解いているということになります。
先ほどの話と合わせて考えると、問題集や参考書での演習だけを行うと、「Step1:分野特定」の訓練が決定的に不足してしまいます。
結果として、知識は頭の中に「単なる情報」としてバラバラにストックされたままになり、プレッシャーがかかった本番で瞬時に取り出すことができません。
ここで、実際の入試問題を用いて話をしていこうと思います。
【1】 aを実数とし,座標空間の点P1(a,0,0),P2(a+1,0,0),,Q(0,1,0)を考える.G1,G2をそれぞれ△P1QR,△P2QRの重心とする.以下の問いに答えよ.(問1) P1,P2を通る直線と,G1,G2を通る直線は平行であることを示せ. (問2) 四角形P1P2G2G1の面積を求めよ. (問3) 四角形P1P2G2G1を底面とする四角錐Q‐P1P2G2G1の体積を求めよ.
これは、2022年の熊本大学の数学の入試問題です。
高校生の時、私は過去問演習でこの問題を解いたのですが、上で説明したStep1にあたる”分野特定”に失敗しました。
「直線」と問題文中にあるから一次関数の知識を使おうと、「xy-平面、yz-平面、xz-平面の三つの平面で、それぞれ直線の式を立てればいい。」と考えてしまい、解くことができませんでした。
しかし、これを通して、高校生の頃の私は「三次元空間上の直線の問題があれば、ベクトルの知識を使える」と学ぶことができました。
このように、初見で解こうとしたときに出てきた”自然な”発想を、「なぜ解答はこのような考え方をしているのか?」や「自分の発想と解答の考え方はどちらが適しているのか?」などのように比較しながら復習すると、分野特定の能力を鍛えることができます。
では逆に、上の問題が問題集で”ベクトルの問題です”と出題されていたらどうでしょうか?
ベクトルの問題と分かれば、「平行」や「面積」などの用語があるので、どのような”ベクトル”の知識を使えばいいか思いつきやすいと思います。
これでは先ほど説明した”自然な”発想が出ることはなく、分野特定の能力が鍛えられることはありません。
これが問題集の演習では得られることができない過去問演習の効果です。
もちろん、問題集の演習が悪いと言いたいわけではありません。
問題集の演習には、各分野の基礎的な内容を効率よく身に着けることができるというメリットがあります。
したがって、入試問題を解けるようにするには、問題集などの演習と過去問演習の二つを両立させる必要があるわけです。
さいごに
過去問や実戦問題は、点数を取るための試験ではなく、皆さんの知識を「入試対応型」に鍛え直すための最高のトレーニング台です。
皆さんが入試問題を解けるような力をつけられるよう、全力でサポートしていきます!
勉強法で迷ったり、相談したいことがあれば、いつでも校舎で声をかけてくださいね!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!